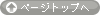【第1章】 『ロッキング・タイム(前編)』
クリスマスを過ぎた12月27日。 あらゆる時計で埋め尽くされた店内に一人の青年が座っていた。 中川正樹、27歳。独身。この中川時計店のオーナー&店長でもあり、唯一の店員でもあった。近くにある石油ストーブで暖をとりながら、着物姿に丹前(たんぜん)を羽織ってモコモコのいでたちである。正樹は愛用の眼鏡の左側にクリップ付きの時計見(作業用ルーペ)を装着して、小さなカウンターテーブルの上で依頼された懐中時計の修理を行っていた。 「ずいぶん使い込まれてるなあ…大事にされてるんだね」 時を刻まなくなった主な原因の第一位は、内蔵されている電池の寿命だ。おそらくこの懐中時計もそうだろう…正樹は分解して電池を取り出すと、在庫の交換用電池を試してみることにした。 「この作業で、今年も店じまい。来年はいい年になるといいなあ」 ラジオから流れる演歌にあわせて口ずさみながら、席を離れて店内の展示用カウンターの足元にある引き戸の鍵をはずし、交換用の電池が入っている箱を取り出す。あとは電池をいれかえて時を刻み始めてくれれば、今年の仕事もおしまいだ。店内を見回して時間をたしかめる。p.m.5:23。閉店まであと一時間半といったところだった。
席に戻って、作業を再開して数分。無事終了したと同時に「バン!」と入り口の扉が悲鳴をあげるのも気にせず、外の凍てつく冷気を帯びながら全身黒衣に包んだ人物が仁王立ちしていた。 「いらっしゃいませ…と、いいたいところですが、乱暴はよしていただけますか?」 正樹の言葉も無視して革靴の音をカン高く鳴り響かせてズカズカと歩み寄りながら、その人物は右手を懐にやり、瞬時にソレをつかむと正樹に向けた…消音装置のついた拳銃だった。 「店を閉めろ。来てもらいたいところがある」 モデル雑誌から出てきたかのような細身で長身の男は、聞き取れるギリギリの声量を発しつつ、正樹の額、数センチ手前に銃口を定めていた。拳銃の安全装置は男のセリフが言い終わらないうちに外される。軽く引き金を動かせば、人生の終止符が待っていた。 正樹が反撃する隙もなく男の動作は完璧で無駄がなかった。相手がサングラスごしなので表情を伺うのは難しい。拒否権のない命令だな…正樹は小さくため息をつき、肩をすくめた。おそらく応じなければ訳もわからないまま中川時計店の閉店記念日になってしまうだろうなあ…と、のんきなことを考える。
「せっぱつまったときこそ、一句でも読める余裕を持っておきたいものじゃな。『悲しい日、泣いてくずれて、明日笑え』とな?」 不器用にウィンクしながら語る人生経験豊富な先代オーナーの言葉がよみがえった。生死不明。たったその四文字で底なしの沼に沈みそうになる…。長い年月が過ぎた今も希望を失わず正樹は戦っていた。 先代オーナーから教わったことは数知れない。ただ残念なことに句を読む才能を受け継ぐことはできなかった。けれど先代の教えに習って窮地の時ほどのんきに構えるようには心がけた。何事も慌てて取り組んだところで100%の結果なんてでないことを今までの苦い経験とともに知っていた。…とはいえ、急ぎの仕事を全力でこなして悔いのないように取り組むことも知らないわけではなかった。
東京都、豊島区。 この場所は、政府による「未来と希望を備え持つ一大都市化計画の構想」のもと、具体化された「輝ける都市計画」事業によって、新たに生まれ変わりつつあった。近々「池袋ネオサンシャインシティ」と改名予定でもある。その象徴が近未来的な大型高層ビルの建設ラッシュであった。池袋中心地に数多く建設され、以前の景観から未来都市へと様変わりしつつあった。それと対極に位置する地域に、正樹の中川時計店は店を構えていた。整備区域の反対運動がもっとも活発だった雑司が谷(ぞうしがや)である。 「伝統的な町並みを残せ!」 「人情あふれる地域を守ろう!」 昔なじみの地域住民たちが掲げたスローガンが、大規模な反対運動にひろがり、街中を大勢の人々が行進する風景を政府も無視できなかった。波紋はインターネット世界にまで広がり、政府は雑司が谷を含む、一部地域の整備を凍結した。が、決してあきらめたわけではなかった。地域住民の怒りが沈静化して事業再開の準備を狙っているというのがもっぱらの噂である。 その昔ながらの雰囲気を残す、雑司が谷にある中川時計店の前には、周囲の景観と不釣合いな黒塗りの高級外国車が異様な雰囲気を漂わせて停車していた。屋根の上に丈夫な鉄格子の様な金属が設置されている。それはルーフキャリアと呼ばれるカー用品の別売り商品だったが、おもに車の屋根に荷物をおくための固定器具として、一般的にはアウトドア向けの車に設置されていることが多い…それが高級外国車に設置されていたのである。正樹は知らなかったが、その車はロールスロイス・ファントムという車種であった。車種を知らなくても、正樹はこれまで高級外国車にルーフキャリアが設置されているのを見たことがなかった。その異様な車の後部座席に否応なく乗せられると、車は静かに発進した。
「下町風情の時計屋を連れ出すには、こんなモノ静かな車で、しかも随分なもてなしですなあ」 正樹が発車間もなく、のんびりとTVドラマの感想をもらすように言葉を発した。エンジン音がまったくしないのだ。おそらく電力がメイン動力なのだろう。ガソリン車と異質で落ち着かなかった正樹は身体的にもそうであった。座り心地の良すぎるふかふかの座席に押し込められ、両手を手錠で拘束され、愛用の眼鏡を無理やりはずされ、代わりにアイマスクを装着という、自由と視界を奪われた中にいたのである。 「ある場所であることをしてもらうためだ。…それ以上のへらず口が出るなら、それを封じる準備もある」 「やれやれ。到着するまで、おとなしくしておきましょう」 正樹の体内時計は車が発進しはじめてから、正確に経過時間を計測していた。どこに向かっているかはわからなかったが、車は信号による一時停車や曲がり角でスピードをおとして進んでいくなどを繰り返し、やがて完全に停止した。池袋から出るには距離が短すぎる…。 しかし、次の瞬間、外部が動いている感覚を感じた。まるで巨大なエレベータで車ごと地下深くに降りていくようだ。気配をうかがっても隣りで銃を構えているであろう男のかすかな息遣いしか聞こえず、運転席の男にいたってはサングラスを同じようにしていたためもあるが、間に設置された遮音ガラスによって何をどうしているかすらわからない。嫌な予感がした。 「池袋の都市伝説を知っているか?」 隣りの男が突然きり出した。ハッキリとした若々しい声量で特徴的だった。 「もうしゃべってもいいのかい?」 正樹の言葉は無視されて男は続けた。 「あるビルの地下駐車場には仕掛けが施されていて、さらに地中深くまでつながっているという謎のエレベータが存在する…それがなんのためか、わかるか?」 「みんなで冬眠でもするのかなあ、今年はいつになく寒いしねえ」 「池袋という地域そのものを、人工的な地震を発生させてふきとばす…地盤を爆破するためだ」 正樹は笑おうとしたが、不完全なものになった。男は本気であり、さらに話は続いた。 「相当な規模の破壊力を持つ爆弾を用意した。その上カウントダウンも始まっている。関係者はここにいる者以外、安全圏まで全員退避済みだ…にもかかわらず、誰かがこの場所を発見し、それを阻止した。起爆装置をおさえられ、何をやっても制御できない。…わかるな? 貴様には封じられた時間を動かしてもらう」 「嫌な注文だねえ」 「選択の余地はない。今、ここで殺されるか…起爆装置の封印を解いて始末されるかの、どちらかだ」 「明るい未来だことで…ところでこの車、かなりゴツゴツとしていたけれど、改造して戦車にでもするのかい?」 全て防弾ガラスに張り替えられ、おそらく知らない改造満載なのは予想できた。気分を入れ替えるために冗談のつもりで言ったのだが返ってきた言葉にその名残はなかった。 「屋根にキャノン砲を搭載予定だ…池袋のある建造物をふきとばすためだ」 正樹は返す言葉が思いつかなかった。この男はいまなんといった? そのとき周囲の下降する感覚がなくなった。アイマスクが外され、愛用のめがねをかけなおすと、手錠をされたまま足元にあった工具箱を持って、男に銃口をつきつけられつつ車を降りた。
薄暗いと感じた瞬間、天井から照明が降りた。そして…自分が巨大な空洞にいることに唖然とした。はかりしれない大空洞が出現していたのだ。しかもさらに驚くべき状況を目撃した。正樹の視線の先に、高さ50メートルはある天井までビッシリと埋め尽くされた軍事用の爆弾兵器が積み上げられていた。正樹はすぐそばまで近寄って片ひざをついて工具箱をおきながら、目を凝らして確かめた。自分の位置は乗ってきた車からおよそ10メートルほどの距離だろうか。積み上げられた爆弾類はかなりの高さがあったが、ドラマなどの撮影用として作られた偽モノなどではなかった。 「貴様ならそれがコケオドシかどうかわかるだろう? …ここは東京ドームが三つほどの空間だ。そこにつめるだけつめた。規模としては池袋を中心に豊島区…いやさらに被害は大きくなるかな?」 男は拳銃から消音装置を外しながら、些細な出来事のように話し、達成される結果には一切興味がない様子だった。冗談じゃない! これらが全て爆発したら巨大地震どころの騒ぎではないだろう。噴火寸前の火山を埋め立ててその上に都市を建設しているようなものだ。その結果がどうなるか…想像するのも恐ろしかった。正樹は想像に恐怖したが、ゆっくりと男に後姿をさらしながら立ち上がった。内心で怒りが沸点にさしかかるのをこらえていたのだ。立ち上がって振り向いたときには、冷ややかなまなざしで男を見ていたが、その正樹の様子に興味があったのか、男が感想をもらした。 「さすがだな…眉一つ動かさず、状況を的確に分析し、その上、我々を欺こうと隙あらば狙っている。…貴様の考えていることはお見通しだ」 銃口を向けられていても正樹は微動だにひるんでいなかった。むしろ、鋭い視線で男に尋ねた。 「誰だお前は?」 男は不適な笑みをこぼして正樹の質問に応じた。 「貴様の過去を知り、貴様が愛する池袋を貴様ごと吹き飛ばしたいと『あの日』から願っていたモノさ」 ゆっくりとサングラスを外す。男の激しい心を投影しているかのようなその瞳は、それぞれが青と紫の輝きに彩られていた。 「アポロン…! まさか…!?」 男はゆっくりと正樹の頭に銃口の狙いを定めた。 「その名で呼ばれるのは久しぶりだな…。そうだ! いまやお前の店となっている古びた時計屋の先代オーナー、穂富 東午(ほとみ とうご)が老いぼれる前に携わっていた自動歩兵(オートファイター)のテスト体、アポロンだ!」 以前の姿とは程遠かった。会話ひとつとってもカタコトの言葉を話すのがやっとだったのだ。それが目の前にいるのは闇の世界に生きる裏社会の人間そのものだ。…大きな組織にひろわれたか。想像は容易だった。軍事兵器として研究開発されていたAI(人工知能)搭載ロボット…それがアポロンの正体であり、目の前の男なのだ。 「この目を覚えていたか…そうでなくてはな! …俺はあの地獄からよみがえった。貴様に絶望と死を与えるためにな!」
瞬間、アポロンは正樹に向けていた拳銃の引き金を引いた。
(To be Continued…)
(*この作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件などにはいっさい関係ありません) |